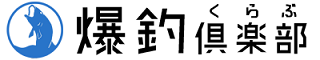ジギングだけではなく、ルアーフィッシングにおいて、ベイトフィッシュの存在は大きなファクターになります。
「ベイトから情報を得る」
まず、一口にベイトフィッシュと言っても、その数は限りないと言っても過言ではありませんが、普段、フィッシュイーターとしてルアーゲームのターゲットと認識する魚種さえも、ジギングのターゲットとする魚種さえも、ジギングでのターゲットとする青物を前にすれば、それらがベイトフィッシュとして捕食されてしまう場面も少なくありません。
たとえ、それが青物であっても、稚魚であればカンパチだろうがブリであろうが関係ありません。
まず、アングラーにとっては気になるであろう疑問点を挙げてみます。
自分の通うエリアのベイトフィッシュは何なのか?
それらのベイトフィッシュはいつ頃に、
どれくらいの規模で入ってくるのか?
そのベイトが入った場合、どのような狙い方が良いのか?
○○パターンなど良く耳にする決まったパターンでしか釣れないのか?

ベイトの動向と傾向を知ってみよう!
まず、エリアによっては、そのシーズンに入ってくるベイトの種類・規模は異なり、青物の捕食パターンも変化していきます。
ベイトフィッシュは規模の大きい群れでの移動がほとんどで、それにより、場合によっては、青物の捕食するベイトは極端に偏ってしまいます。

このような状況に陥ってしまうと、ジグには全く反応しないという状況も珍しくありません。
加えて、一年のほとんどがその海域に見られるベイトもいれば、一定の時期のみに回遊を見せて、そのシーズンが終わるとパッタリと消えてしまうものもいます。
それ以外にも、これまでは回遊が見られなかったのに、ある時期から急に異例のベイトフィッシュが入ってきたりと、ベイトフィッシュにもそれぞれの行動パターンが存在します。
今回、このジギングの「キーポイント」ともなるベイトフィッシュの中でも代表的な魚種を紹介します。
ジギングに限らず、一般的なベイトフィッシュとしての認識も非常に高い魚「イワシ」。
中でもカタクチイワシは、日本で最も漁獲量が多く、その群れの規模は非常に膨大です。
イワシは、天候に左右されやすい傾向が高く、晴天時が続くと表層に浮く傾向があり、曇り・雨天時は中層~ボトム付近にまで沈む事が多く見られます。
天候に左右されやすいイワシの場合は、逆にその的を絞りやすいとも言えます。
個体数も多く、必然的に青物のベイトフィッシュになりやすく、加えて、その動向も把握しやすいとなると、アングラー側もベイトがイワシであることが分かっていれば、イメージが湧きやすいのではないでしょうか?

【全国的に数が多いカタクチイワシ】
青物も含めて多くの魚種のベイトになる魚です。

【子イカ】
玄界灘では12月頃、蒲江沖は夏、地域によって差異が見られます。
【カタボシイワシ】
鹿児島ではカタボシイワシがブリを釣れてくる事も多くあります。
イワシだけでなく、他の多くのベイトフィッシュにも当てはまる事ではありますが、「ベイトから情報を得る」ということで言えば、ベイトフィッシュが青物に追い詰められ、海面がバシャバシャと沸き立つ「ナブラ」があります。
これは、一目で見るからに、食い気がある状況が確認できます。
ただ、食い気があるから確実に釣れるというわけでは、決してありません。もちろん、そこに投げれば、いとも簡単に釣れてしまうという状況もありますが、前途しているような、「偏食」をしてしまっている、またはそれに近い状況なのか、全く反応してくれない事もあります。
ここでは、ベイトフィッシュについて、ほんのさわりの部分だけ書きましたが、ただ目の前にあるエサを食べている‥というような単純な事だけではない事が分かって頂けたと思います。
このベイトフィッシュの情報を得るというのは、ジギングだけだはなく、全てのルアーゲームに通じる事でもあります。
ベイトフィッシュを踏まえた上での応用テクニックを覚えていく事が、釣果を伸ばす一番の近道です。
何度も言いますが、ルアーフィッシングにおいて「ベイトから情報を得る」ということが、皆さんのターゲットとする魚を釣り上げるための最も重要なポイントではないでしょうか。