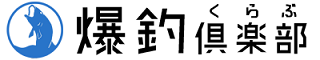深山に潜む渓流の王者イワナ(岩魚)は、棲息する地域によって体色や斑紋などに違いが見られます。
日本国内のイワナ属の魚は、イワナとオショロコマの二種でオショロコマは北海道のみに棲息していますが、本種は北海道から本州南西部まで広く分布しています。
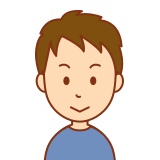
そんな渓流の王者イワナを釣る為の基本的な釣り方を4つご紹介します。
まず、食性からみていきましょう。
イワナの生態
イワナは、水温15℃以下の冷水を好む為、標高の高い山岳渓流の最上部に棲息しています。
イワナの食性は、極めて貪欲なことで知られていますが、川底の石裏に潜むカゲロウやトビゲラなどの幼虫・成虫、アブやトンボ、セミ、バッタ、クモ類といった昆虫を好んで捕食しています。
流れの中に居る小魚やカニも常食としており、ミミズやトカゲ、ヘビ、カエル、ネズミなどにも果敢にアタックしてくる悪食家です。
イワナ独特の習性とは・・?
イワナの警戒心は非常に強く、不用意に人間が近付くと物陰に隠れて、数時間姿を現さなくなります。
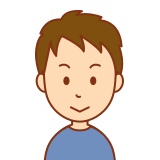
イワナって見えても素早く岩陰などに隠れますよね。
警戒心が強いから隠れたところにキャストしてもなかなか釣れません。
大雨などによる増水を機敏に察知する能力をもち、川底の砂利を胃袋に蓄えて急流でも流されない工夫をするなど、独特の習性を持ち合わせています。
釣り方
極めて神経質なイワナですが、悪食なので、釣り人が流す餌には簡単に食いついてしまう側面もありますので、テクニックうんぬんよりも、イワナの魚影が多い場所にアプローチすることの方が重要といえるでしょう。
ミャク釣り
変化の多い渓流に潜むイワナは、シンプルなミャク釣り仕掛けで狙うのが、一般的です。
渓流竿
川の規模・状況に合わせて5.1m~6.3m程の長さを使い分けましょう。
仕掛け
道糸一本通しが基本、または竿を振れないプッシュ帯では、道糸を短くしたチョウチン仕様が使いやすいです。
餌
クロカワムシなどの川虫類やミミズが万能で、夏の時期には、バッタやアブ・トンボなども有能な餌です。
岩陰や流れの落ち込みに仕掛けを投入し、餌が自然に流れるように操作しましょう。
テンカラ釣り
テンカラ釣りでは、専用の竿とラインが快適に使えますが、ラインについてはテーパーのないレベルラインも多用されています。
毛バリは市販品を利用したり、自分でオリジナルを巻く楽しみ方もあります。
キャスト方法
竿をムチのようにしならせ、その反動で毛バリをキャストするのが基本です。うまく投げる為のコツは、竿を握った腕の脇を締め、なるべくコンパクトに竿を振りましょう。
キャストした毛バリは自然に流し、時折、竿先で誘いを入れるのも効果的で、魚が毛バリにアタックしてきたら、軽く手首を起こしてアワセを入れてください。
フライフィッシング
フライフィッシングのターゲット魚としても人気の高いイワナです。
使用するタックルは、3~5番のロッドにフローティングラインの組み合わせが使いやすいでしょう。
フライフィッシングはイワナ狙いに効果的?
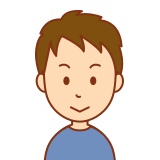
使用するフライは、シーズン初期はメイフライなどのドライフライやニンフが有効ですが、6月頃以降は、アリや甲虫といった陸棲昆虫を摸してテレストリアルの独壇場になります。
釣り方
カディスなどの万能フライを使って、イワナが潜むポイントを叩きます。ここぞというポイントでは、好みのフライを試したり、状況によってはマーカーを使ったルース二ングで攻めてみるのも良いでしょう。
ルアーフィッシング
小魚も貪欲に捕食するフィッシュイーターであるイワナは、当然、ルアーへの反応も抜群にいい魚です。
渓流では、ライトアクションのトラウトロッドに小型スピニングをセットし、ルアーは小型ミノ―やスプーン・スピナーなどを用意しましょう。
朝マズメ・夕マズメ時は、浅瀬に出ているイワナを静かに狙い、日中は、餌釣りでは狙えないような大きな滝壺や瀬などを積極的に攻めてみるのも良いです。
なお、山上湖やダム湖では、ルアーをトローリングで引いて大型のイワナを狙う事も可能です。
簡単!美味しいイワナの食べ方
イワナの身は、見た目に似合わず驚くほど上品でおいしく食べられます。
代表的なイワナ料理といえば、なんといっても河原で味わう「塩焼き」ではないでしょうか。
夏のイワナは脂もたっぷり乗っていて、焚き火でじっくりと焼いたときに河原に漂う香ばしさは格別なものがありますね。
さらに、源流のイワナだからこそ味わってみたいのが、「刺身」です。イワナは川魚特有の臭みが皆無で、濃厚なうま味を堪能できます。
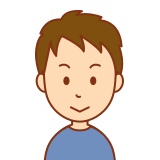
ただし、河川によっては寄生虫の存在もありますので、刺身を味わう時は注意が必要ですね。
他には、フライや燻製、煮付け・香草焼き、内臓の塩辛などでも、渓流魚ならではの美味しさを味わう事ができます。
さいごに
基本的な4つのイワナの釣り方は、いかがでしたか?
清らかで冷たい水を好むイワナは、渓流域の中でも、最上部を棲み処としており、夏でも残雪の残る山岳エリアでは釣り人の姿も少なく、大物と出会える可能性も秘めてます。
山形県にある大鳥池のタキタロウ伝説のように、謎に包まれた大型魚ゲットも夢ではないかも知れません。